2022年北京中医薬大学
「鍼の自律神経調節に関するトップ100専門誌掲載論文の文献分析」
A bibliometric analysis of 100 top-cited journal articles related to acupuncture regulation of the autonomic nervous system
Zhanhao Zhao et al.
Front Neurosci. 2022 Dec 22;16:1086087.
以下、引用。
日本の佐藤昭夫はもっとも引用された論文著者だった。最も自律神経と鍼について書いた国はアメリカで次は日本、3位中国、4位スウェーデン、5位韓国、6位ドイツ、7位台湾だった。佐藤昭夫はトップ100論文で最も引用された著者であり、体性自律神経機能について調査した。
このビブリオメトリック分析は非常に印象的でした。
1990年代初めに佐藤昭夫先生が発表された論文が、自律神経と鍼に関するもっとも引用された論文です。
「故佐藤昭夫先生の研究成果から見た自律神経と鍼灸」
佐藤 優子、 内田 さえ、野口 栄太郎、今井 賢治、, 小俣 浩
『全日本鍼灸学会雑誌』2010 年 60 巻 4 号 p. 672-692
1990年代前半までは日本は世界の鍼灸研究の中心地でした。
1950年代の良導絡、あるいは経絡現象や赤羽幸兵衛先生の研究は中国にも影響を与えました。
1955年には柳谷素霊先生がフランスに渡り、半年間滞在してパブロ・ピカソをはじめとする有名人を治療しました。
1961年には本間祥白先生がドイツ・ミュンヘンの国際鍼灸学会に招かれて「陰陽五行説による日本の鍼灸」を講演しました。
1964年には岡部素道先生が弟子の木下晴都先生と共にヨーロッパ・アジア・東南アジアを学術講演旅行します。
1965年に第1回の国際鍼灸学会が上野の東京文化会館で開かれますが、初代会長は岡部素道先生でした。間違いなく、鍼灸の臨床は日本が世界のトップでした。
1971年に中国の鍼麻酔が鍼灸ブームを起こすと生理学畑の人々が大量流入し、日本でも1980年『全日本鍼灸学会』の成立を促しました。これは世界中で起こったメディカル・アキュパンクチャーの流れです。日本はずっと内臓体壁反射の研究で世界をリードしていました。
1990年代前半までは科学的研究でも世界のトップだったのです。
1991年にゴードン・ガイアットが最初のEBМ論文を書きます。
1997年にアメリカNIHが鍼の効果の科学的根拠を認めるNIH声明を行います。
2000年代に中国がWTOに参加して急激な経済成長を成し遂げます。
1991年に冷戦が終結し、日本のバブル経済が崩壊し、1995年にウィンドウズ95が発売されてインターネット革命が起こります。EBМ革命は2000年代ドイツのジャーマン・メガ・トライアル大規模臨床試験で鍼の痛みへの科学的根拠を確立しました。インターネット革命とEBМ革命の流れで、アメリカと中国の鍼研究が強力になります。
2014年にラトガーズ医科大学のルイス・ウリョア先生が『ネーチャー』の論文で革命を起こしました。
2020年8月にはハーバード大学の馬秋富先生が鍼による迷走神経を介した抗炎症作用の論文を発表します。
以下、引用。
ルイス・ウリョアは、2014 年に「ドーパミンは、電気鍼による迷走神経を介しての免疫システムの調節を媒介する」を発表した。これは317 件の引用があり、最も引用されている動物実験である。馬秋富は最近の 2 つの記事「電気鍼療法によるニューロペプチドY発現交感神経経路の駆動における体性組織と強度依存性」と「迷走神経軸を駆動するための電気鍼治療の神経解剖学的基礎」をそれぞれNeuronとNatureに発表した。耳鍼と同様のメカニズムである 経皮性耳介迷走神経刺激taVNS は、過去 20 年間でさまざまな疾患を治療するための確立された治療オプションになった。
ルイス・ウリョア先生の迷走神経の抗炎症作用の研究、馬秋富先生の迷走神経の抗炎症作用の研究、耳介の経皮性迷走神経刺激が現在の鍼の自律神経研究のホットスポットになります。
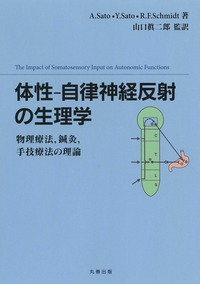









コメント